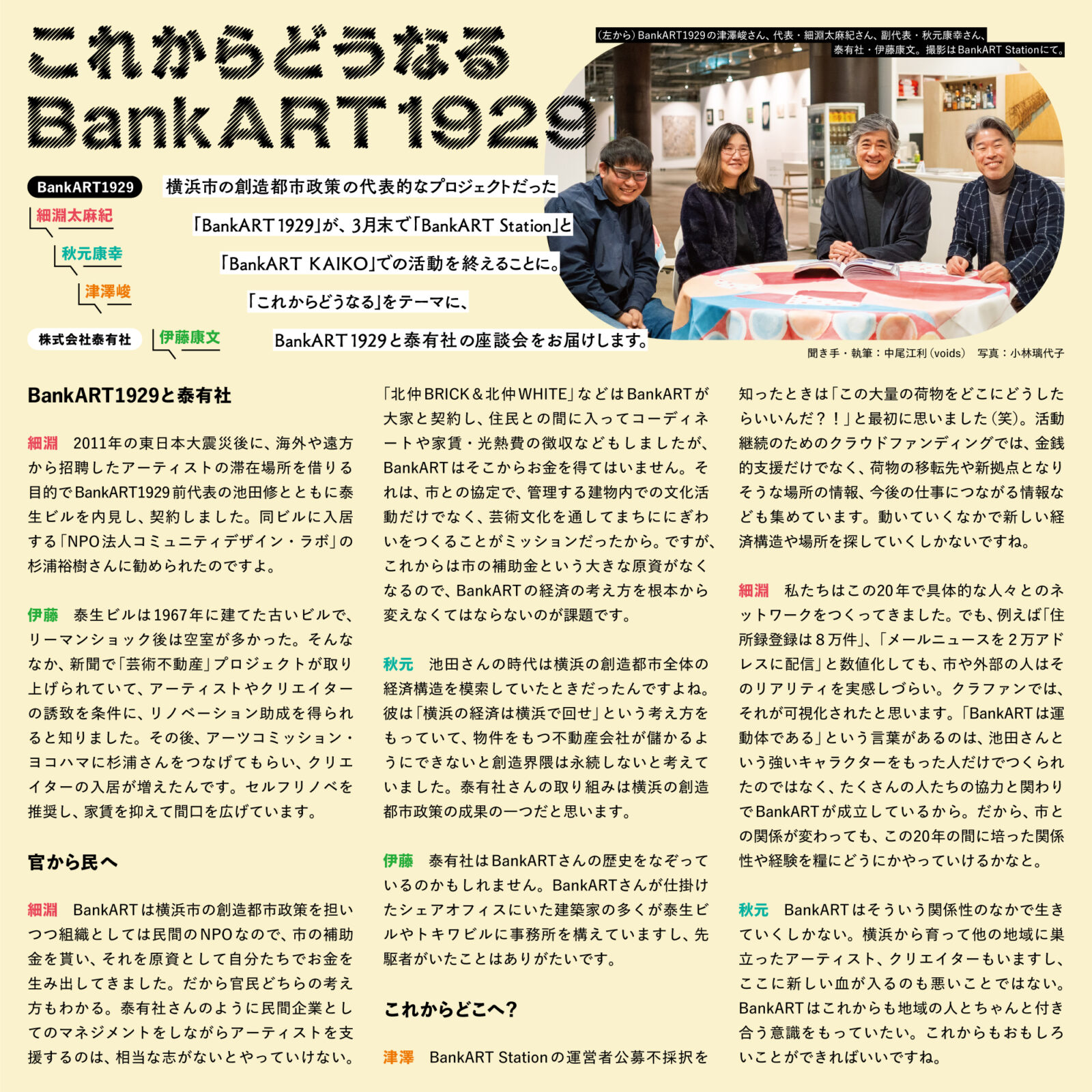横浜市の創造都市政策の代表的なプロジェクトだった「BankART1929」が、3月末で「BankART Station」と「BankART KAIKO」での活動を終えることに。「これからどうなる」をテーマに、BankART1929と泰有社の座談会をお届けします。

BankART1929と泰有社
細淵 2011年の東日本大震災後に、海外や遠方から招聘したアーティストの滞在場所を借りる目的でBankART1929前代表の池田修とともに泰生ビルを内見し、契約しました。同ビルに入居する「NPO 法人コミュニティデザイン・ラボ」の杉浦裕樹さんに勧められたのですよ。
伊藤 泰生ビルは1967年に建てた古いビルで、リーマンショック後は空室が多かった。そんななか、新聞で「芸術不動産」プロジェクトが取り上げられていて、アーティストやクリエイターの誘致を条件に、リノベーション助成を得られると知りました。その後、アーツコミッション・ヨコハマに杉浦さんをつなげてもらい、クリエイターの入居が増えたんです。セルフリノベを推奨し、家賃を抑えて間口を広げています。
官から民へ
細淵 BankARTは横浜市の創造都市政策を担いつつ組織としては民間のNPOなので、市の補助金を貰い、それを原資として自分たちでお金を生み出してきました。だから官民どちらの考え方もわかる。泰有社さんのように民間企業としてのマネジメントをしながらアーティストを支援するのは、相当な志がないとやっていけない。
「北仲BRICK&北仲WHITE」などはBankART が大家と契約し、住民との間に入ってコーディネートや家賃・光熱費の徴収などもしましたが、BankARTはそこからお金を得てはいません。それは、市との協定で、管理する建物内での文化活動だけでなく、芸術文化を通してまちににぎわいをつくることがミッションだったから。ですが、これからは市の補助金という大きな原資がなくなるので、BankARTの経済の考え方を根本から変えなくてはならないのが課題です。
秋元 池田さんの時代は横浜の創造都市全体の経済構造を模索していたときだったんですよね。彼は「横浜の経済は横浜で回せ」という考え方をもっていて、物件をもつ不動産会社が儲かるようにできないと創造界隈は永続しないと考えていました。泰有社さんの取り組みは横浜の創造都市政策の成果の一つだと思います。
伊藤 泰有社はBankARTさんの歴史をなぞっているのかもしれません。BankARTさんが仕掛けたシェアオフィスにいた建築家の多くが泰生ビルやトキワビルに事務所を構えていますし、先駆者がいたことはありがたいです。
これからどこへ?
津澤 BankART Stationの運営者公募不採択を知ったときは「この大量の荷物をどこにどうしたらいいんだ?!」と最初に思いました(笑)。活動継続のためのクラウドファンディングでは、金銭的支援だけでなく、荷物の移転先や新拠点となりそうな場所の情報、今後の仕事につながる情報なども集めています。動いていくなかで新しい経済構造や場所を探していくしかないですね。
細淵 私たちはこの20年で具体的な人々とのネットワークをつくってきました。でも、例えば「住所録登録は8万件」、「メールニュースを2万アドレスに配信」と数値化しても、市や外部の人はそのリアリティを実感しづらい。クラファンでは、それが可視化されたと思います。「BankARTは運動体である」という言葉があるのは、池田さんという強いキャラクターをもった人だけでつくられたのではなく、たくさんの人たちの協力と関わりでBankARTが成立しているから。だから、市との関係が変わっても、この20年の間に培った関係性や経験を糧にどうにかやっていけるかなと。
秋元 BankARTはそういう関係性のなかで生きていくしかない。横浜から育って他の地域に巣立ったアーティスト、クリエイターもいますし、ここに新しい血が入るのも悪いことではない。BankART はこれからも地域の人とちゃんと付き合う意識をもっていたい。これからもおもしろいことができればいいですね。
聞き手・執筆:中尾江利(voids)
写真:小林璃代子